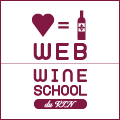ワイン 百一話
珍陀酒(ちんとしゅ) (Part 3)
2010/07/16 PART 01 | 02| 03| 04
1639年のポルトガル船の来航禁止以降は、オランダが長崎の出島に通商館を開きます。ヒュースケンの記録によると、オランダ側が主催して出島で行う、日本人向けの接待では<招待客の日本人たちは、酸っぱい赤ワインはあまり好まなかったが、火酒やシャンペンを大層好み、しばしば何回にも渡って所望したので、酒庫が空になるくらいだった>と、書かれてあれます。
歴史に強い読者ならば、ここで「江戸時代と一口にいっても、ヒュースケンは江戸時代も相当終わりの頃の人物である」と思われたでしょう。その通りです。
オランダ人が振る舞った火酒とは、蒸留酒でありウオトカのようなとても強い酒のことを指します。蒸留酒は、ワインから造ればブランデー、ビールから造ればウイスキー、清酒から造れば焼酎ですが、蒸留する前段階のアルコールの原料は、とくにこの際問題にしません。ただ、オランダから輸入される蒸留酒(火酒)の原料はワインではなかったと推測されます。
なぜならば、オランダの地理的条件は、先のポルトガルとはまったく正反対で、あまりにも北にあるために、太陽の恵みが不足し、ぶどうはとても出来ません。他の国で出来たワインを輸入して火酒を造るのではコストがかかり過ぎます。そこで、原料を別に求めるか、あるいは出来上がった蒸留酒を買いつけたでありましょう。
蒸留の技術に関しては、これは難しくありません。そもそも、海水を蒸留して水を得る方法はエジプト時代より以前からあるのです。