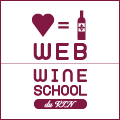ワイン 百一話
小説にでてくるワイン 1 (Part 1)
2011/05/24 PART 01 | 02| 03| 04| 05
映画や絵画と同様、小説にもワインはしばしば登場します。
R・コンドン作「ワインは死の香り」では主人公がワインの強奪をはかり、R・ダール作「味」では18歳の娘をブラインド・テイスティングの賭けに使うなどとんでもない話が載っています。
それに比べて、D・リンジ作「悪魔が目をとじるまで」では、ブルゴーニュの赤ワインが男と女を結びつける役目を果たします。
J・アーチャー「泥棒たちの名誉」はワイン通と自認する人ならば、一度はそのうわさを聞いたことがありそうな、有名な作品です。この小説はつぎのような流れでした。
カンジ悪〜い大金持ちとワイン協会の会長を務める男が、ブラインド・テイスティングで賭をします。
大金持ちは、自分のセラーに眠るワインを四本選びだして、会長にブラインドさせます。賭金は200ポンド。会長はもちろん自他共に許す、ワイン業界の大御所。しかし、彼は出された4本のワインの銘柄や生産年を、ことごとくはずしてしまいます。
大金持ちの勝ち誇った表情が、目に浮かびます。しかし会長は、平然としていて悪びれたところは、全くありません。賭に敗けたのですから、200ポンドを支払います。
ここで著者は、執事がひとり真っ青になっていることを、読者に告げるのです。執事がワインを入れかえていたのですね。